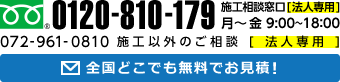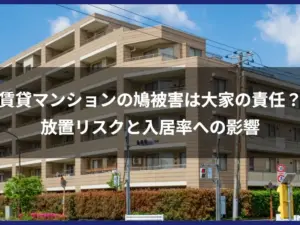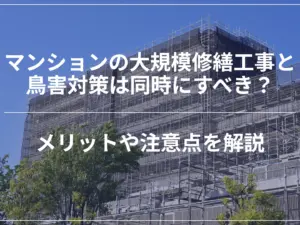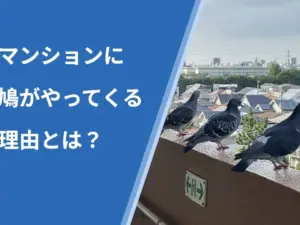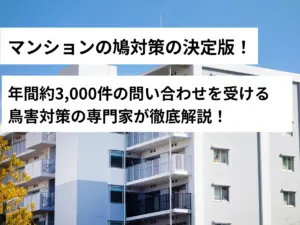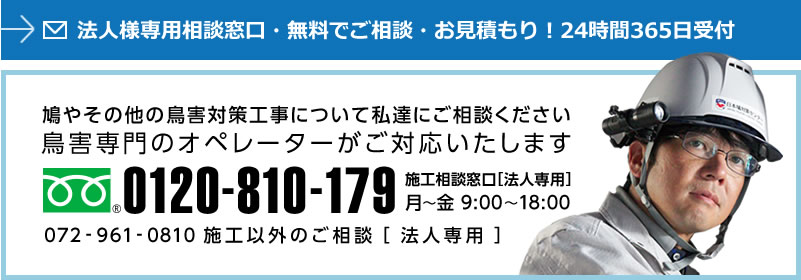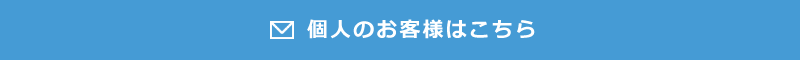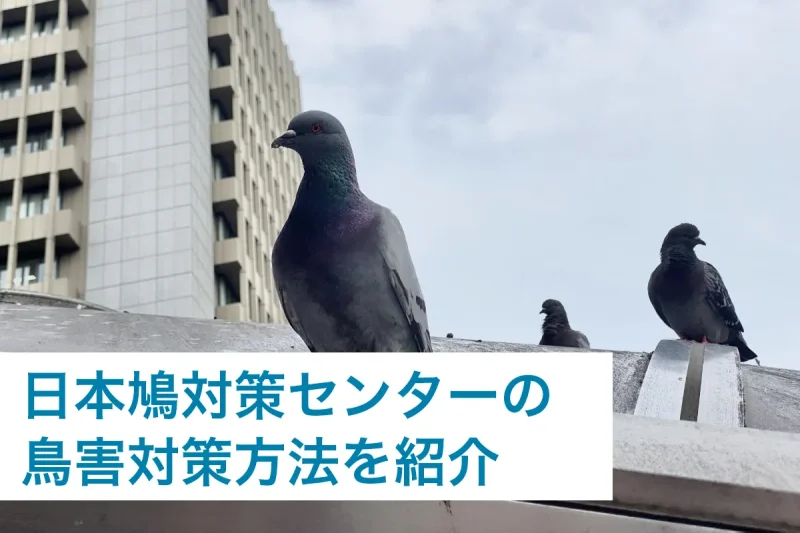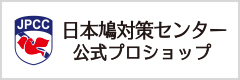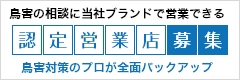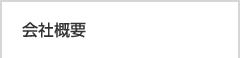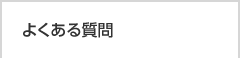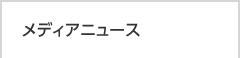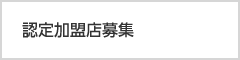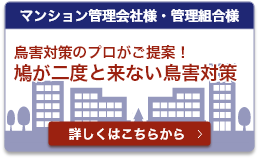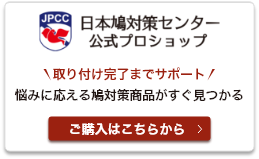鳩対策/2025.09.29
賃貸マンションの鳩被害は大家(オーナー)の責任?放置リスクと入居率への影響
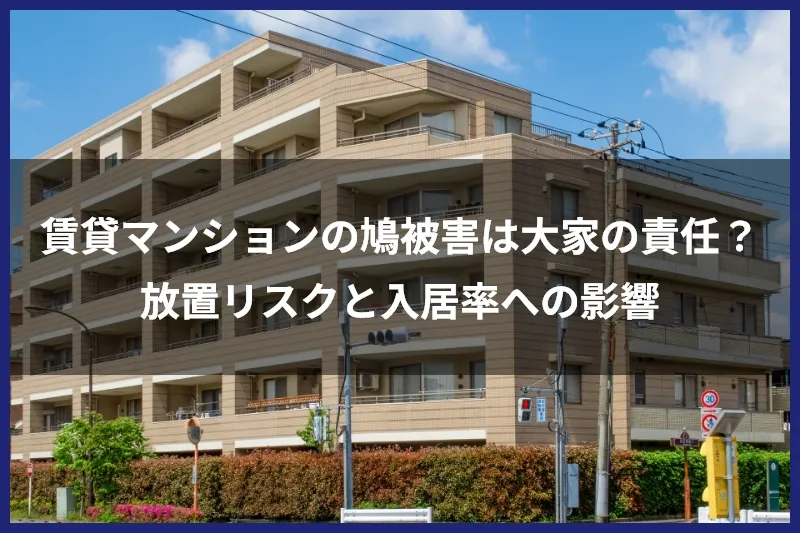
賃貸マンションを経営している方や管理している方の中で、鳩被害に悩まされている方は多いのではないでしょうか。ベランダや屋上、非常階段などに鳩が住み着いてしまい、糞害や騒音に困っているケースも珍しくありません。
鳩の糞は酸性のため、建物の外壁や設備を腐食させて長期的な構造劣化を引き起こします。また、糞にはクリプトコックス症などの感染症を引き起こす可能性がある真菌や様々な健康被害の原因となる細菌等が含まれており、入居者の健康にも悪影響を与える可能性があります。
さらに、鳩が住み着くと早朝からの鳴き声による騒音問題、巣材から発生するダニなどの衛生問題も発生します。一度住み着いてしまうと繁殖を繰り返して数が急増するため、マンションの資産価値や入居率にも深刻な影響を及ぼしかねません。
この記事では、鳩被害における責任の所在と、放置することで生じるリスクについて詳しく解説します。また、鳩対策が賃貸経営にもたらすメリットや具体的な対策方法についても、専門家の知見を交えながらお伝えします。
目次
- 鳩被害は大家の責任?知っておくべき管理の基本
- 賃貸マンションオーナーが鳩対策をすることで得られるメリット
- 入居率アップにつながる!賃貸マンション大家が取り入れやすい鳩対策
- 鳩被害が収まったら鳩対策は不要?再発防止の考え方
- 鳩対策は賃貸経営の価値を上げる前向きな投資
1: 鳩被害は大家の責任?知っておくべき管理の基本

賃貸マンションで鳩被害が発生した場合、その責任は誰にあるのでしょうか。管理会社、大家、入居者のうち、一体誰が対策費用を負担すべきなのか、法的な観点から整理していきましょう。
一般的に、賃貸物件における鳩被害への対応は、大家側の責任として問われるケースが多くなっています。これは建物の共用部分や構造に関わる問題として扱われるためです。
管理会社が関わる場合でも、管理を完全に委託している場合は管理会社が対応を検討しますが、最終的な費用負担については管理会社とオーナーで協議し、オーナー負担で対策するパターンがほとんどです。
ただし、入居者が餌やりをしていたなど、鳩を呼び込む行為をしていた場合は入居者の責任となります。この場合、ベランダの設備破損や清掃費用などは入居者負担となる可能性があります。
1-1: 共用部の衛生・安全管理は大家の義務
賃貸マンションにおいて、屋上、非常階段、廊下などの共用部分の衛生・安全管理は、基本的に大家の義務とされています。これらの場所で発生する鳩被害についても、大家が対応すべき管理責任の範囲に含まれます。
ベランダの管理については法的な位置づけが複雑です。専用使用権が設定されている場合が多いものの、構造的には共用部分とされることが一般的です。そのため、鳩対策のような建物全体に関わる問題については、大家側で対応するケースが多くなっています。
管理規約で鳩対策について明記している物件はまだ少ないのが現状です。しかし、衛生管理や近隣への迷惑防止の観点から、今後は管理規約に盛り込む物件も増えてくると予想されます。
保健所からの指導を受けるケースも実際に発生しています。特に集合住宅で鳩の糞による健康被害が発生した場合、行政側から衛生管理の改善を求められることがあります。こうした指導を受けた場合、大家側は速やかな対応が求められます。
1-2: 放置による健康被害やクレーム・賠償リスク
鳩被害を放置することで発生する健康被害は、クリプトコックス症だけではありません。鳩の糞や羽毛はダニやノミの発生源となり、これらがアレルギー反応を引き起こすケースもあります。
特に鳥アレルギーを持つ方にとって、鳩の糞や羽毛によるアレルギーは深刻な呼吸器系の健康被害を引き起こす可能性があります。また、糞自体が様々なアレルギーの原因物質となることも報告されています。
実際に市営住宅で、住民ではない来訪者がクリプトコックス症を発症し、市側が全面的に対策費用を負担したケースもあります。こうした事例からも分かるように、鳩被害は訴訟や損害賠償につながる可能性があります。
特に、糞害だけでなく鳩被害が原因で病気を発症したり、重篤な健康被害が生じた場合は、管理責任を問われるリスクが高くなります。予防的な対策を怠った結果として法的責任を追及される可能性もあるため、早期の対応が重要です。
1-3: 管理体制が入居者からの信頼につながる
鳩対策の実施状況は、入居者の満足度に大きな影響を与えます。適切な対策が取られている物件では、入居者から「管理がしっかりしている」という評価を得やすく、長期入居にもつながります。
入居者の中で鳩対策の有無を気にする方は決して少なくありません。特に小さなお子様がいる家庭や、アレルギーなど健康リスクをかかえている方、衛生面に敏感な方にとって、鳩対策は物件選びの重要な判断材料となっています。
口コミサイトや評価サイトで鳩対策について触れられることは、現在のところそれほど多くありません。これは、多くの物件で鳩対策が十分に行われていないことの表れでもあります。しかし、物件情報を提供する際に鳩対策の実施状況を明記することで、差別化要素として活用できる可能性があります。
逆に、鳩被害が放置されている物件では、入居者からのクレームや早期退去のリスクが高まります。特に内見時に糞害が目立つ状態では、入居希望者に悪い印象を与えてしまい、入居率の低下は避けられないでしょう。
H2-2: 賃貸マンションオーナーが鳩対策をすることで得られるメリット

鳩対策は単なる問題解決だけではなく、賃貸経営にとって多くのメリットをもたらします。初期投資は必要ですが、長期的には収益性の向上や資産価値の維持につながる重要な投資といえるでしょう。
鳩対策を実施している物件の割合は、現在のところそれほど高くありません。都市部で鳩が多く生息している地域では周辺の物件で対策を取っているケースもありますが、鳩がそもそも少ない地域では対策を講じている物件はほとんど見当たりません。
つまり、鳩が生息している地域で先手を打って対策を実施することで、他の物件との差別化を図ることができるのです。この差別化は入居率の向上や家賃設定の優位性につながる可能性があります。
また、鳩対策の実施前後で劇的な入居率の変化を示すデータは限られていますが、被害が深刻な状態から対策を実施した場合、明らかに入居希望者の反応が改善されるケースが多く報告されています。
2-1: 見た目と衛生の改善で内見時の印象アップで入居率もアップ
内見時の印象は入居率に直結する重要な要素です。鳩の糞で汚れたベランダや悪臭のする共用部は、内見者に非常に悪い印象を与えてしまいます。
内見者から鳩被害について質問されることは珍しくありません。特にベランダや屋上付近で糞害が目立つ物件では、「鳩の対策はしているのか」「今後改善される予定はあるのか」といった質問を受けることが稀にあります。
一方で、防鳥ネットや防鳥剣山などの対策設備が設置されている場合の内見者の反応は複雑です。対策がされていることは評価される一方で、ネットの存在により「鳩被害があった」ことが明らかになってしまうため、物件の資産価値にマイナスの影響を与える可能性もあります。
そのため、理想的なのは被害が発生する前の予防的対策です。電気ショックシステムなど、外観に影響を与えない対策であれば、予防効果を得ながら物件の美観を保つこともできます。
既に被害が出ている場合でも、「何もしないで汚い状況」と「対策をして鳩がいない状況」を比較すれば、明らかに後者の方が入居率にプラスの影響を与えます。
2-2: 糞害、騒音などのクレーム減・退去防止で収益が安定
鳩被害が原因で退去率が上がってしまうケースは決して稀ではありません。特に小さなお子様がいる家庭では、衛生面への不安から早期退去を選択するケースが見られます。
鳩による騒音問題も深刻です。早朝からの鳴き声や羽音により、睡眠を妨害される入居者からのクレームが寄せられることがあります。また、ベランダが使用できない状況では、洗濯物を干せないなどの実用面での問題も発生します。
こうしたクレームが継続すると、入居者の満足度が大幅に低下し、更新時の退去につながりやすくなります。退去が発生すると、原状回復費用や新たな入居者募集のコスト、空室期間中の家賃収入の損失など、多額の損失が発生してしまいます。
鳩対策を実施することで、これらのクレームを未然に防ぎ、入居者の満足度を維持することができます。結果として長期入居が促進され、安定した家賃収入の確保につながります。
2-3: 管理意識の高さをアピールできる差別化要素に
現在のところ、募集広告で鳩対策済みを積極的にアピールしている事例はまだ多くありません。しかし、これは逆に言えば、鳩対策をアピールポイントとして活用できる余地が大きいということでもあります。
管理会社からの評価は、対策実施後に明らかに向上するケースが多く報告されています。「問題に対して迅速に対応してくれるオーナー」として信頼を得ることができ、管理会社との良好な関係構築にもつながります。
特に管理意識の高さは、入居者だけでなく管理会社にとっても重要な評価ポイントです。問題が発生した際に適切な対応を取るオーナーの物件は、管理会社としても安心して管理を任せられる物件として評価されます。
また、近隣の物件で鳩被害が発生している中で、自分の物件だけが清潔に保たれている状況は、明確な競争優位性となります。こうした差別化要素は、家賃設定や入居者選定においても有利に働く可能性があります。
3: 入居率アップにつながる!賃貸マンション大家が取り入れやすい鳩対策

鳩対策は段階的に実施することが可能で、予算や状況に応じて適切な方法を選択できます。まず重要なのは、現在の被害状況を正確に把握することです。
「鳩が見え始めた」というお客様の相談の多くは、実際にはすでに住み着いている状況がほとんどです。鳩が来ているということ自体、多くの場合は予防段階を過ぎていることを意味します。
対策の手順としては、まず現地調査を行い、被害の程度を確認します。本当に被害が出ていない初期段階であれば、電気ショックシステムが最も効果的です。費用は対象物件の規模や施工の難易度によって80万円から200万円程度と幅がありますが、陸屋根であれば施工しやすく費用を抑えられます。三角屋根の場合は足場やロープ作業など安全対策が必要なため、費用が高くなる傾向があります。
すでに住み着いている場合は、基本的に防鳥ネットと剣山の組み合わせによる対策が必要になります。
3-1: 防鳥ネットや剣山、電気ショックなど効果的な対策例
各対策方法にはそれぞれ特徴があり、状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。
電気ショックシステムは、鳩が止まりやすい場所に設置することで、その場所を「危険」と学習させる方法です。外観への影響が最小限で、予防効果も高いため、被害が出る前の対策としては最も優れています。ただし、すでに住み着いている鳩には効果が限定的です。
防鳥ネットは、物理的に鳩の侵入を防ぐ最も確実な方法です。大きな面積をカバーする場合は剣山よりもコストが安く済みます。網目は5cm角程度で、鳩の侵入を完全に防ぐことができ、外観への影響もさほど感じないでしょう。
剣山は、配管のL字部分や監視カメラの上、ダクトなど、部分的な対策に適しています。大きな面積には向かず、コストも高くなりがちですが、ピンポイントでの対策には有効です。
薬剤による対策もありますが、臭いやベタベタした感触の問題があり、半年に1回程度の塗り替えが必要です。執着心の強い鳩には効果が限定的で、結果的に高コストになることが多いため、あまり推奨されていません。
台風や強風に対する耐久性については、防鳥ネットは細くて軽いため、強風レベルであればそれほど影響を受けません。ただし、台風レベルの風になると、ネットが壁に擦れて破れたり、飛来物によって破損する可能性があります。こうした自然災害による破損は有償での修理対応となります。
3-2: 専門業者に任せると安心・確実・ラク
DIYでの鳩対策と専門業者による対策では、効果に大きな違いが生まれます。最も重要なのは、鳩の生態や行動パターンを正しく理解しているかどうかです。
専門業者選びで失敗しやすいパターンとしては、鳥のことを十分に理解せず、単純に「ネットを張れば良い」程度の認識で対応する業者を選んでしまうことです。なぜその対策が必要なのか、この場合はどのような方法が適しているのかを、理論的根拠に基づいて説明できる業者を選ぶことが重要です。
また、鳩対策専門の材料ではなく、一般的な防鳥ネットや受注生産の剣山を使用する業者、薬剤で簡単に済ませようとする業者は、専門知識や技術が不足している可能性があります。また、鳥害対策専用のネットや剣山でないとネットの隙間から鳩が侵入したり、剣山の上に鳩が止まるなど、失敗するケースが非常に多くあります。 結果的に費用をかけたのに問題が解決しないということになります。
近年、鳩対策業者は急激に増加していますが、その多くが、エアコン業者や清掃業者、賃貸管理の設備業者が副業的に始めたケースも多く、鳩の生態に基づかない適当な対策を行う業者も存在します。
保証内容については、施工不良による再発には5年間の無償保証が一般的です。ただし、台風などの自然災害や第三者による破損、建物自体の劣化(塗装の剥がれなど)による不具合は有償対応となります。
費用相場は対策範囲や建物の構造によって大きく異なりますが、マンション1棟全体の対策で数百万円程度を見込んでおく必要があります。工期は規模にもよりますが、一般的には数日から1週間程度です。
3-3: 大規模修繕と同時に実施すればコスト削減も
大規模修繕と鳩対策を同時に実施することで、足場設置費用などの共通コストを削減できます。具体的な削減率は案件によって異なりますが、足場代だけでも相当な節約になる場合があります。
修繕計画に組み込む際の注意点としては、鳩対策の必要性を事前に十分検討し、修繕のタイミングまで被害が拡大しないよう配慮することです。修繕まで時間がある場合は、暫定的な対策を先行して実施することも検討すべきです。
また、修繕業者と鳩対策業者の連携が重要になるため、事前の調整や工程管理をしっかりと行う必要があります。修繕後に鳩対策を行う場合は、修繕で使用する材料や仕上げが鳩対策設備の設置に影響しないかも確認しておくことが大切です。
4: 鳩被害が収まったら鳩対策は不要?再発防止の考え方

鳩対策を実施して被害が収まったとしても、対策は継続する必要があります。これは、鳩が来る根本的な原因である餌場がなくならないためです。
対策実施後の再発率について、適切に施工された場合の施工不良による再発はほとんどありません。見落としや接着不良などがあった場合でも、5年間の保証期間内で無償対応されます。ただし、建物の劣化による取り付け部分の不具合は有償対応となります。
一時的に現在住んでいる鳩がいなくなったとしても、餌場がある限り別の鳩がやってくる可能性は高いです。そのため、たとえ被害が収まっても、最低限の予防策は継続することが重要です。
4-1: 一時的に減っても再び飛来するケースが多い
鳩被害は季節による変動があります。春から秋にかけては活動が活発になり、夏や冬場は比較的見かける頻度が少なくなる傾向があります。しかし、これは一時的な減少であり、暖かくなれば再び活動が活発になります。
周辺環境の変化も鳩の飛来に大きく影響します。隣接するマンションで鳩対策が実施された場合、そこにいた鳩が一気に移動してくる可能性があります。こうしたケースは決して珍しくなく、「隣で対策をしたら突然うちに来た」という相談は頻繁に寄せられます。
また、餌場の状況変化も影響します。近くに新しい公園ができたり、餌やりをする人が現れたりすると、鳩の活動範囲が変わり、新たな住処を探し始めることがあります。
このように、一度対策をして効果があったとしても、外部環境の変化により再び鳩が飛来するリスクは常に存在します。そのため、継続的な監視と予防策の維持が重要になります。
4-2: 「今は大丈夫」なうちに予防策を検討
予防投資と事後対策では、費用に大きな差が生まれます。被害が出る前の電気ショックシステムによる予防であれば、ネットと剣山の組み合わせよりもコストを抑えることができます。
早期対策のタイミングを見極めるポイントは、鳩の行動段階を理解することです。屋上のパラペットやベランダの手すりに鳩が止まり始めた段階が警戒信号です。これは「待機」の段階で、その後「住み着き」の段階に進行する前に対策を講じることが重要です。
また、隣接するマンションでの鳩の状況も重要な判断材料になります。隣のマンションに鳩が多く住み着いている場合、そこで対策が実施されれば自分の物件に移ってくる可能性が高いためです。
空を飛んでいる鳩の群れを頻繁に見かけるようになった場合も注意が必要です。近くに住み着いている鳩の群れが分裂して新しい住処を探している可能性があります。
近隣での餌やりの情報も重要です。餌場が近くにできると、その周辺での鳩の活動が活発になり、住処を求めて建物に近づいてくる可能性が高まります。
4-3: 入居者から”ずっと清潔”と思われる管理体制へ
継続的な鳩対策は、入居者に「この物件はいつも清潔に管理されている」という印象を与えます。これは入居者の満足度向上と長期入居の促進につながる重要な要素です。
一度対策を実施した後も、定期的な点検とメンテナンスを行うことで、問題の早期発見と迅速な対応が可能になります。こうした管理体制は、入居者からの信頼獲得にもつながります。
また、「問題が起きてから対応する」のではなく、「問題を未然に防ぐ」管理姿勢は、他の設備管理や建物メンテナンスに対する入居者の安心感にもつながります。
予防的な管理体制は、結果的にクレーム対応の手間や突発的な修繕費用を削減し、安定した賃貸経営にも寄与します。
5: 鳩対策は賃貸経営の価値を上げる前向きな投資

鳩対策は単なる問題解決ではなく、賃貸経営の価値を向上させる積極的な投資として捉えることができます。適切な対策により、建物の資産価値維持、入居率向上、管理コスト削減など、多面的なメリットを得ることができます。
不動産査定時に鳩対策の有無が直接的に評価されるケースはまだ少ないものが、建物の維持管理状況は査定に影響する要素の一つです。鳩被害により外壁や設備に損傷が生じている物件と、適切に管理されている物件では、当然ながら評価に差が生まれます。
今後、人口減少や空室率の増加により、賃貸物件間の競争はさらに激しくなることが予想されます。その中で、鳩対策をはじめとする適切な建物管理は、他の物件との差別化要素としてより重要性を増していくでしょう。
5-1: 空室対策+建物維持で資産価値アップ
鳩の糞による建物への被害は想像以上に深刻です。糞の酸性成分により外壁塗装が劣化し、コンクリートや金属部分にも腐食が進行します。実際に、鳩被害により外壁の修繕費用が大幅に増加したケースも報告されています。
特に、排水溝に糞が蓄積して詰まりが生じ、雨水の適切な排出ができなくなることで防水層に負荷がかかり、結果的に大規模な防水工事が必要になったケースもあります。こうした修繕費用は数百万円規模になることも珍しくありません。
また、設備機器への影響も深刻です。室外機周辺に糞が蓄積することで、機器の効率低下や故障の原因となる場合があります。給排気口への糞の詰まりにより、建物全体の換気システムに影響が出ることもあります。
これらの被害を予防することで、建物の長期的な資産価値を維持し、大規模な修繕費用の発生を抑制できます。鳩対策の初期投資は、将来的な修繕費用の削減効果を考慮すれば、十分に回収可能な投資といえるでしょう。
5-2: 清潔で快適な住環境が長期入居につながる
清潔で快適な住環境は、入居者の満足度向上と長期入居の促進に直結します。鳩被害のない物件では、入居者が安心して生活でき、更新時の継続率も高くなる傾向があります。
長期入居が増えることで、入居者募集の頻度が減り、仲介手数料や原状回復費用などのコストを削減できます。また、空室期間の短縮により、安定した家賃収入を確保することも可能になります。
さらに、良好な住環境は入居者同士のトラブル減少にもつながります。鳩被害によるベランダ使用制限や騒音問題がなくなることで、入居者間の関係も良好に保たれやすくなります。
5-3: 鳥害のない賃貸マンションが入居者から選ばれる時代へ
今後の市場トレンドとして、人口減少により空室率が上昇し、賃貸物件間の競争が激化することが予想されます。この中で、鳩対策をはじめとする適切な建物管理は、重要な差別化要素となっていくでしょう。
特に都市部では、空室の増加により鳩が住み着きやすい環境が増える可能性があります。空室の多い物件は人の出入りが少なく、鳩にとって理想的な住処となりやすいためです。こうした環境変化により、鳩被害のリスクは今後さらに高まることが予想されます。
また、入居者の衛生意識や生活品質への関心も年々高まっています。特に若い世代や子育て世代では、住環境の清潔さを重視する傾向が強く、鳩被害のない物件を積極的に選ぶ動きも見られます。
先進的な取り組みとしては、新築時から鳩対策を織り込んだ設計を行う物件や、管理規約に鳩対策を明記して継続的な対応を保証する物件なども現れています。また、太陽光パネル設置時に同時に鳩の侵入防止策を講じるなど、予防的な対策を標準化する動きも見られます。
市営住宅や公団住宅においても、入居率の低下に伴い鳩被害が増加する傾向があります。こうした公的住宅での対策事例が増えることで、民間の賃貸住宅でも鳩対策が標準的な管理業務として認識されるようになることが予想されます。
鳩対策は、もはや「問題が起きてから対応する」ものではなく、「快適な住環境を維持するための予防的投資」として位置づけられる時代が来ています。早期の対策実施により、入居者に選ばれる物件づくりを進めていくことが、今後の賃貸経営成功の鍵となるでしょう。
 タグ
タグ